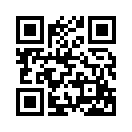2007年06月25日
赤の意味は?

食いしん坊の私ですが、山桃を賛美するための画像ではありません。テーマの「赤」にいいと思ってのことです。前回のワイルドベリーの赤はもっと光り輝いています。身びいきで輝いて見える訳ではありません。色は色だけで表現されるのではなく、素材感が重要だということを、わかっていただけますか。同じ果実でも、イチゴの表面は、滑らかで、光が特定の方向に反射され、山桃はつぶつぶデコボコしているため、いろいろな方向に反射されるためです。この写真は雨上がりのため、光沢を感じますが・・・
ということは、赤といっても、たとえ、色相、明度、彩度(色の三属性といいます)が同じでも、他の条件が異なれば違って見えるということです。素材感は勿論、自然光(太陽光でも一日中同じでないことは、誰もが経験で知っています)と人工光(これも、様々な種類があります)、他にも心理的な条件があります。見るときの、その人の気持ちが影響するのも心理的条件ですが、人間の眼が持つ特性により起こる錯覚も、心理的な見え方の一つといえます。
また、人は、眼があれば見えるのではなく、その情報が脳に伝達されて、画像解読をした結果として、初めて色や形を認識できることから、簡単に推測できるように、記憶による判断が、「見え」に大きな影響を与えます。
記憶色という言葉をご存知ですか。これは色彩を人類学、言語学等の分野からの検討の結果、定義づけられた言葉のようですが、私たちが、経験の積み重ねで記憶の中に作った物の色のことです。
わかりやすく言えば、イチゴという果実に、私たちは経験で、”イチゴの色はこういう色”というカテゴリーで記憶しているということです。「赤色」といわれた時、頭に浮かぶのは、このようにして積み上げられた「赤色」のカテゴリーに入れられた赤だということです。正確に言えば、個人個人で、「赤」に対するイメージは違うということになります。
色の意味とかカラーセラピーとかいっても、ここが難しいところです。その人の個人的な経験を乗り越える、或いはヒーリング効果があると信じるのは、行き過ぎというものでしょう。それは、心理療法であって、完全に医療行為です。こういう誤った過大な期待を抱いて、色をみるのではなく、人類の文明が始まった当初から、人々が、神の領域に属するものとして、憧れ、大切にしてきた宝物である「色」を誰もが気軽に楽しめるという、視点で、色の意味を、少しずつ紹介していく予定です。
赤については、次回。内容は、「原色と2次色」の説明と、獰猛な色「赤」のイメージとシンボリズム。お楽しみとして、オーラについても少し書こうかと思います。