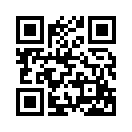2007年07月18日
ハーブ工房


ハーブ工房と言うほどではありませんが、香り袋に使用する無農薬有機栽培のハーブの一つです。右の写真のものを収穫して、左端が6ヶ月かけて、室内の清浄な空気の中でゆったりと乾燥したものです。抱えきれないほどの量が、半分以下になります。真ん中は、茎の部分で、左端が、葉です。使用するのは葉の部分のみですから、収穫時の枝の20分の1~30分の1位の量に減ってしまいます。そのまま使えれば一番いいのですが、時間を経て使う場合、きれいな所で十分乾燥させなければ、カビや虫が発生します。
ハーブにより、乾燥する時間は異なりますが、これは、特に乾燥が難しいハーブです。乾燥しにくいということ以上に、乾燥の仕方、収穫時期で、収穫する部分等で、香りが変わってしまいます。
ラベンダー、ローズマリー等は香りが安定しているのですが、このレモンマリーゴールドは素晴らしい香りを残すのが本当に難しいハーブです。そのためか、ハーブ園に行っても見ることはあまりありませんし、乾燥して使われてはいません。この香りを何とか残したいと結構長い年月いろいろやっています。まだ、満足できる段階までは至っていませんが、香り袋の素材として使い始めています。
ハーブを解体するのは、香りがいいし優雅と思われるかもしれませんが、かなり、きつい作業です。異物が入るのは困るので、清潔に洗った素手で一本一本取り外していく訳ですが、乾燥しているから、かなり痛いし、うんざりするほど時間がかかります。育てて、収穫し、乾燥、解体と考えてみれば一年がかりの作業です。
こうして作った幾つかのハーブと天然樹木で最も抗菌力に優れ、気品のある芳香を持つ天然青森ひばの木粉・精油を使って作るのが、カラコ特製香り袋です。すべて日本産をモットーに、時として遊び心で御香を少量隠し味に使っています。
大変でも、調合している時の楽しさは特別です。何色の袋に入れようかなと考えならが・・・・・・
2007年07月13日
美味しい!!!!!

カラコ特製ポーク丼。醤油を、適宜まわしかけて、たべます。肉の美味しさを味わうために、かけすぎないことが肝心です。私が料理名人ということではありません。素材がよければ、技は必要ないということです。ポーク君が違います。通常の飼育とは異なり、抗生物質、ホルモン剤を一切餌に添加しないで飼育した育ちのいい健康ポークです。
生まれた時から、抗生物質、ホルモン剤を一切使用しないで飼育した家畜は、あまりいません。何しろ、人間に使われる抗生物質の何倍もの量が飼育に使われているのですから。流通している殆どの肉には、使用されていると思った方がいいでしょう。
使用しないで飼育しようという試みも一部で行われています。放牧、放豚、放鶏等により、自然の飼育をやっているところもありますが、市場に流通するコストでの生産は難しく、特別な方法でしか入手できないのが現状です。
再度言上。ほんものは、オイシイ! 秘伝のたれも、達人技も必要ない。
まさに、そのまんま丼。
カラコのモットー 「シンプル・イズ・ビューティフル」にピッタリの食材です、感謝。
何しろ、肉のピンクを見ただけでも、唾液を垂らしそうになります。
桜色を生かすために、器は黒にしました。
本当に美味しいものに出会うと、現金なもので、元気が出るだけでなく、機嫌までよくなります! 続きを読む
2007年07月11日
国際競争ー色

これから、色のことを投稿する時は、この映像を使います。これは、マンセル色相環という、マンセル表色系の色の環で、色を伝えあうためのシステムの一つです。
色を伝える時、どうするかということなど、多分、色の研究が科学の最先端テーマだった時代にはあまり問題ではなかったのだと思います。色は、どうして見えるのかとか、色とは何だとか、どうしたら混色で透明感のある美しい色を作れるかとかが重要問題であって、色を、詳細に伝える必要性はありませんでした。私たちが今でも使っている、空の色、海の色、芽吹きの時の葉の色、土の色、リンゴの色、オレンジの色、太陽の色、夜明けの色などなど、それに多彩な表現をつけることで、十分表現されていました。それが、他の国に行くと、空色と思っていた空ではなく、土の色も違い、同じように太陽が見えても、自分たちは黄色と思っていたのに、この国では太陽は赤いというとか、様々な矛盾にぶつかり、その中から、色の表現方法を考える人がでてきました。特に、合成染料が次々と色を生み出していくに従い、色は、以前にも増してお金を生むもの、産業として重要となりました。1856年世界初の合成染料モーブは、発明者パーキンが特許出願し、認められたものです。その後次々と合成染料が作られ、色を広く売る時代になると、色の詳細な表現が求められるようになりました。そんな中、人種の坩堝であった米国では、表現の統一は、何処より、重要問題だったのでしょう。画家マンセルが、色を表現するシステムを考案し、色票集をつくり、その後修正されたものが現在も国際的な基準として使われています。マンセルの発表から100年を経ていることを考えると、すごいの一言です。この色を伝える重要性が、米国では他のどこの国より敏感だったためでしょうか、その後のカラー戦争では、車の色を初め、受話器の色、家電の色と、「色を売る」先人を切り、遂には、ケネディ・ニクソンのテレビ論戦では、カラーテレビの効果を最大限に利用して、若々しく凛々しい大統領像をテレビの前の米国民に印象付けたケネディが、優勢であったニクソン破ったことで、カラーコーディネートの重要性を国家の最重要事項である大統領選で照明しました。
私たちは、日常的には気が付いていませんが、色の表現方法というのは、その国の言語が何かということと同じ問題です。どのシステムを使うかということは、どの言語にするかということと同じといえる訳です。
色の先進国では、どこでも、自分の国のシステムを他の国にも使って欲しい訳です。それはそうでしょう。日本語が英国や仏国、米国でそのまま通じるとしたら、便利だけでなく、文化で占拠している証であり、経済的政治的にどうかという面は抜きにして、純粋に日本人として誇らしいですから・・・・・
ノーベル賞受賞者である、ドイツの科学書オストワルトによるシステム、ヘーゲルの心理4原色に則ったNCS等、マンセル表色系より合理的な美しいシステム、また、機械を使った工業的なシステムが他にありますが、表色系といえば、米国は現在もマンセルです。
日本は、1900年半ばに、マンセル表色系に準拠した色の表現方法がJIS規格となっています。PCCS、CICCは日本のカラーシステムですが、明度基準、色相にマンセルを使っており、どちらのシステムもマンセルと互換性があるように作られています。でも、日本は、トーン【色調)を、システムに組み込むことで日本独自のカラーシステムを作っています。それは、日本特有の中間色文化が土台にあってのことでしょう。 続きを読む
2007年07月06日
天草ゼリー


急な注文で、昨夜は、ほぼ徹夜状態。でも、美味しいことは勿論、美しく出来たので、大満足です。
これは、県外に出荷です。そうなのです、カラコ開発の天草ゼリーは、知る人ぞ知る、生きたままの植物性乳酸菌を封じ込めてある健康食というだけでなく、"美味しい”が大前提の優れもの(自画自賛ではありません)。
材料は、安心安全が第一ですから、自分の目で確認可能な材料を使っています。メインの天草は、最高級品の西伊豆産。ともかく、暑い。天草=暑い といっていいほど、辛抱してしっかりと煮出すしかないのです。植物性乳酸菌は、熱と酸に強いスーパーマン。
フルーツは、「ゼリーにしてみたら?」というお言葉と共に、いろいろな方から、無農薬有機栽培の素材がカラコの元に届けられます。ありがたく、嬉しい限りですが、時々、参ることもあります。製造が時間的に無理な時は、徹夜の道しかない!
今回の素材もいただき物で作りました。それで、出荷するのは図々しいなど、言わないでください。くださった方には、ちゃんと、特製ゼリーで還元しています。カラコの天草ゼリーが大好物で、材料をくださる訳で、私が何処へ出荷しましたと報告しても、天草ゼリーさえ手に入れば、そんなことはどうでもいいのです。
プラムの赤がルビー色で、美しかったので、もう一種類は、白ワインと白桃にしました。きれいに仕上げると、シアワセ

2007年07月03日
幼児の色認識

以前ちょっと書きましたが、はじめは、赤ちゃんは色としての認識はないといわれています。赤ちゃんには、明るいか暗いかだけです。生後2,3ヶ月の頃から、違いを意識し始め、6ヵ月位で、ようやく原色の識別ができるようになります。一番すきなのは、勿論、一番明度の高い原色、黄色です。明るい色だからパステルトーンが好きな訳です。
では、どうやって、赤は"あか"、青は"あお”と認識するようになるのでしょう。
「それは、覚えていくんだよ」と、賢い皆さんは回答されるでしょう。その通りです。色彩語が、経験の言語といわれる所以です。
若いママに忠告です。子供の中には、「赤」と教えても、「きいろ」とか「みどり」とかしか答えてくれない子もいるのです。その時、早急に、「うちの子は、色弱かしら?・・・・」と、ドキンとして悩まないで下さい。実は、カラコはその手の子を経験しているのです。その時、その時、言うことが変わると気が付き、「もしかしたら、色盲じゃないかもしれない。でも、それなら、何故、色がわからないのだろう。えっ、色もわからない子なの?」と、幾日も悩み続けました。別に他に変な所がある訳でもないのに、どうしてなの。賢いお年寄りに聞いても、何も答えてもらえませんでした。
ある日、彼に、「○○くん」「なに?」と返事をされた時、あっと思いつきました。「あのね、この色、な~に?」と、赤い色紙を見せると、案の定、元気いっぱい「きいろ!」と叫びました。「違うのよ。これは、赤よ」「”きいろ”だもん」と、ここまではいつもの会話です。「あっそう。じゃ、△くん」「・・・・・・」「△くん。お返事して」「ぼく、△じゃないもん。○○だもん」「何故?」「だって、それが僕の名前だもん」と、大憤慨してくれました。「じゃ、この子の事は、”あか”って呼んでやってね。」「・・・・・・」極めつけの強情者は、まだ抵抗していましたが、「名前だから、仕方ないのよ、ねっ?」で、やっと納得してくれて、即刻、すべての色をその名前で呼んでくれるようになりました。
これは、彼が、2歳になったばかりの事件でした。 続きを読む