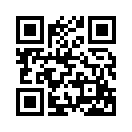2007年07月03日
幼児の色認識

以前ちょっと書きましたが、はじめは、赤ちゃんは色としての認識はないといわれています。赤ちゃんには、明るいか暗いかだけです。生後2,3ヶ月の頃から、違いを意識し始め、6ヵ月位で、ようやく原色の識別ができるようになります。一番すきなのは、勿論、一番明度の高い原色、黄色です。明るい色だからパステルトーンが好きな訳です。
では、どうやって、赤は"あか"、青は"あお”と認識するようになるのでしょう。
「それは、覚えていくんだよ」と、賢い皆さんは回答されるでしょう。その通りです。色彩語が、経験の言語といわれる所以です。
若いママに忠告です。子供の中には、「赤」と教えても、「きいろ」とか「みどり」とかしか答えてくれない子もいるのです。その時、早急に、「うちの子は、色弱かしら?・・・・」と、ドキンとして悩まないで下さい。実は、カラコはその手の子を経験しているのです。その時、その時、言うことが変わると気が付き、「もしかしたら、色盲じゃないかもしれない。でも、それなら、何故、色がわからないのだろう。えっ、色もわからない子なの?」と、幾日も悩み続けました。別に他に変な所がある訳でもないのに、どうしてなの。賢いお年寄りに聞いても、何も答えてもらえませんでした。
ある日、彼に、「○○くん」「なに?」と返事をされた時、あっと思いつきました。「あのね、この色、な~に?」と、赤い色紙を見せると、案の定、元気いっぱい「きいろ!」と叫びました。「違うのよ。これは、赤よ」「”きいろ”だもん」と、ここまではいつもの会話です。「あっそう。じゃ、△くん」「・・・・・・」「△くん。お返事して」「ぼく、△じゃないもん。○○だもん」「何故?」「だって、それが僕の名前だもん」と、大憤慨してくれました。「じゃ、この子の事は、”あか”って呼んでやってね。」「・・・・・・」極めつけの強情者は、まだ抵抗していましたが、「名前だから、仕方ないのよ、ねっ?」で、やっと納得してくれて、即刻、すべての色をその名前で呼んでくれるようになりました。
これは、彼が、2歳になったばかりの事件でした。 続きを読む